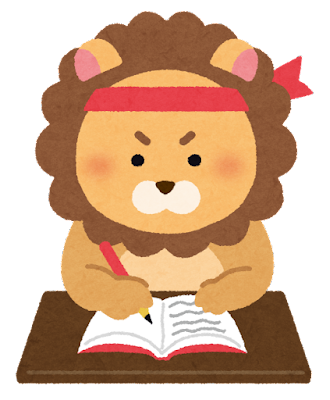公務員の副業解禁はいつから?元公務員の経験から解説します
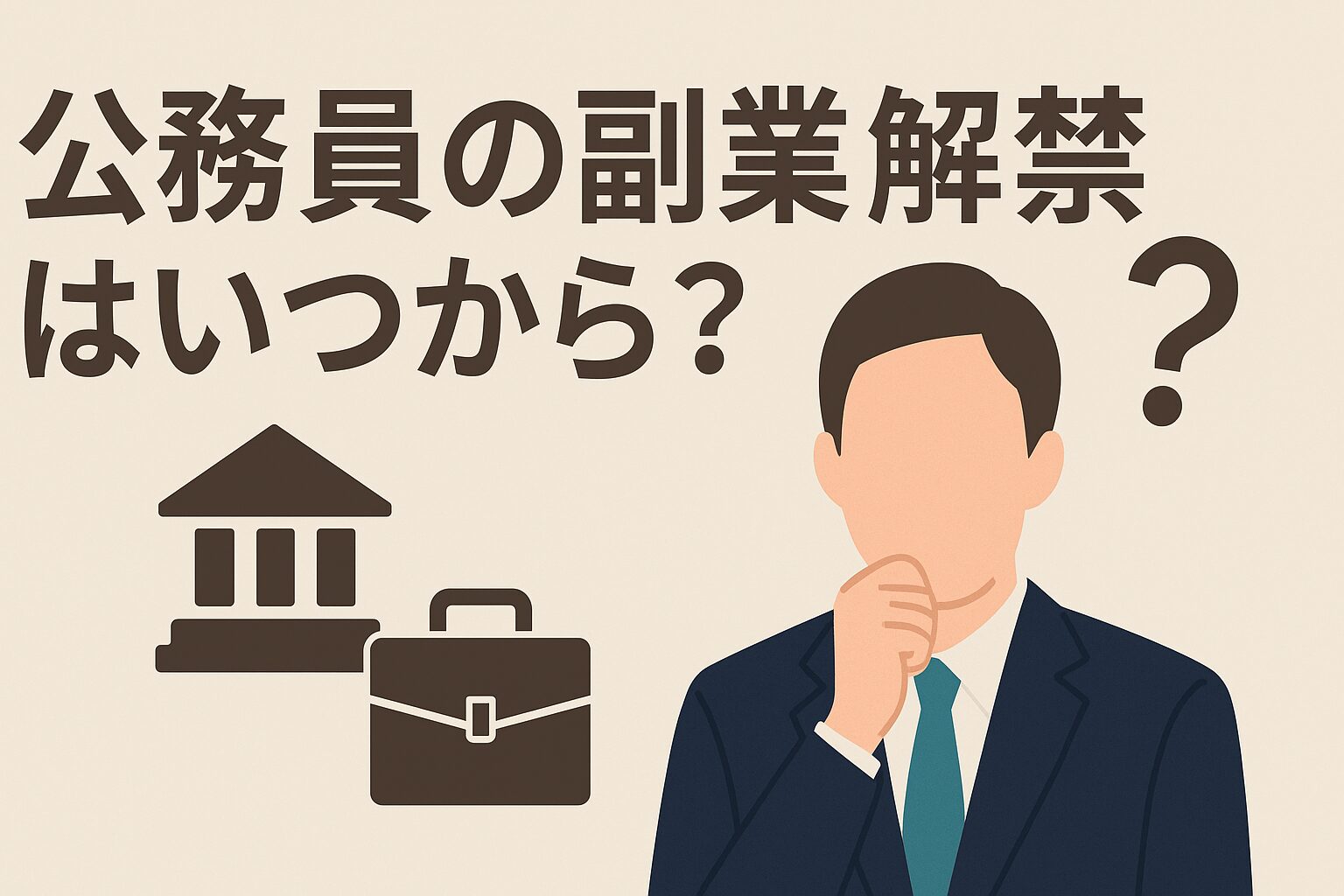
「公務員はいつ副業できるようになるの?」
「現時点で公務員が出来る副業は何?」
「この先公務員の副業はさらに緩和されていくの?」
など色々とお悩みではありませんか?
私も公務員の副業ってあまりイメージがピンとこなくて、安易に請け負って服務規律に違反してしまったらどうしようかと思っていました。

思わぬ形で処分を受けるのは困りますよね。
その原因は、公務員の副業におけるルールを理解していないためです。
実は公務員の副業は、一部認められています。
なぜなら、規則上では「副業はダメ」という表現はないからです。
しかし、営利目的はNGで、公益性の高いものは申請によって認められる場合があります。
つまり、副業の形でよくある
・商品売買(せどり)
・アルバイト
は申請しても認められることはありません。
この辺りの曖昧な部分について具体的に解説していきます。
私は元公務員として20年勤続し、その間公務員でありながらも兼業をしている方も見てきました。
そんな私の経験を含めた内容をお伝えします。
公務員の副業解禁はいつから?【もとから禁止ではない】
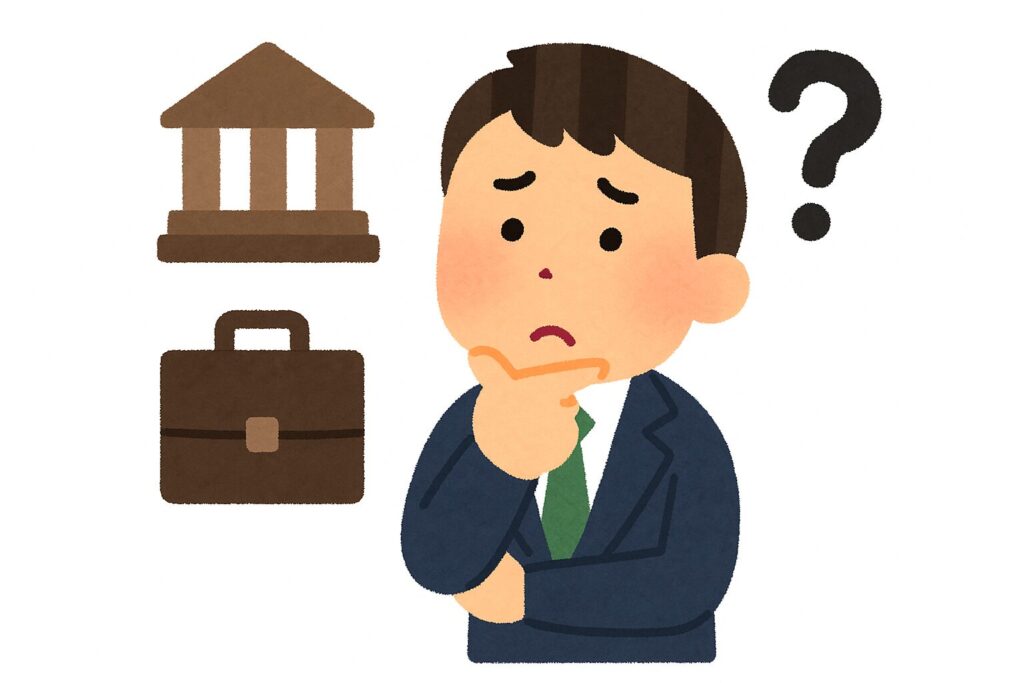
「公務員は副業が禁止されている」と広く思われていますが、実はこれは正確ではありません。
法律上、公務員の副業は「原則禁止」されているものの、すべてがNGというわけではなく、一定の条件を満たせば認められるケースもあります。
例えば、営利を目的としないボランティア活動や、所属長の許可を得た上で行う執筆・講演などは、正式に承認されれば可能です。
実際に、多くの自治体や省庁では、こうした活動について個別に判断される運用がされています。
つまり「いつ副業が解禁されるのか」と未来を待つよりも、現在すでに許可される可能性のある副業を知り、制度の中で上手に立ち回ることが重要です。
副業に興味がある公務員の方は、まずは「禁止」ではなく「条件付きで認められることがある」という視点に切り替えることから始めましょう。
※2025年6月に総務省から各自治体に対し、副業に対する見解が示されました。
凝縮してまとめると以下の通りです。
・公務員の兼業は「禁止」ではなく「許可制」
・①本業の能率が下がらない②利害がぶつからない③品位を損なわない
・時間は週8時間・月30時間以内が目安で、報酬は社会的に妥当な範囲
・営利企業での兼業も条件次第で認められる方向
・各自治体はガイドラインを整備し、職員の成長や地域貢献につながる取組を推進
→だいぶ柔軟に受け止められることになった。
(参考:総務省)
人事や上司に相談しながら、ルールを確認し、正式な手続きを踏めば、副収入を得る道も見えてきます。
【実は結構ある】公務員ができる副業は?

現状では具体的にどのようなものが認められているのか見ていきましょう。
なお、近年では公務員の人手不足から、副業の捉え方を拡げている自治体もあるようです。
NPO法人活動
NPO法人は特定非営利活動法人であり、営利目的ではありません。
そのため、許可さえあれば公務員も取り組めます。
また、無報酬であれば許可も不要ですが、本業に支障をきたすことのないよう注意が必要です。
なお、公益性が高い事業や地域に貢献する活動は認められやすくなります。
講演活動
公務員が専門知識を生かして行う講演は、許可を得ることで副業として認められています。
例えば
・地域の防災講座
・教育の専門家として講義
などが挙げられます。
これにより、地域住民に役立つ情報を提供しながら副収入を得ることができます。
しかし、このような講演活動で報酬を得る際には、事前に勤務先からの許可が必要です。
活動内容や報酬に関して詳細な申請を行い、許可を取得することで正式に兼業で活動を行えます。
執筆活動
専門分野に関する書籍や記事の執筆も、公務員の副業として認められる場合があります。
例えば
・法律関係の公務員が法律解説書を執筆する
・教員が教育専門書を執筆する
・その他各専門誌の原稿執筆
などです。
これにより、読者に有益な情報を提供しつつ、執筆料を収入として得ることが可能です。

執筆活動も事前に勤務先の許可が必要です。
報酬の有無や執筆内容について詳細な申請を行い、許可を得ることが求められます。
小規模農業
自給を目的とした小規模農業も、副業として認められる場合があります。
具体的には、引き継いだ農地を荒らさないために人に貸し、農作をしてもらうことで収入や成果物を得ることです。
この活動も内容によっては許可が必要です。
特に、営利目的でないかどうかを事前に活動内容や販売計画で詳細に示し、勤務先からの承認を得ることが重要です。

講演や執筆に関しては許可申請が面倒だということで謝礼は受け取らないって人もいるとか・・

ボランティアですか・・・
田舎の自治体では農業が盛んで、私の同僚でも同じケースで「農業所得」を得て確定申告していました
※2025年6月以降の弾力化で、今後新たな事例が増えてくることが予想されます。
いずれにせよ、申請し許可は必要なので注意しましょう。
公務員が多くの副業を制限されるシンプルな理由

「副業で収入を増やしたい」と考える公務員は増えています。
しかし、公務員には副業制限があり、自由に稼ぐことは難しいのが現実です。
では、なぜ公務員は副業を制限されるのでしょうか?
その理由をシンプルに3つ紹介します。
1.公務の公平性を保つため
公務員の仕事は、国民に対して公平・公正でなければなりません。
しかし、副業を自由にすると
「特定の人や企業に便宜を図るのでは?」
という疑念が生じ、公務への信頼が揺らぎます。

例えば、税務職員が個人で税務相談の副業をしていたらどうでしょう?
「この人に頼めば税金が安くなるかも」と考える人が出るかもしれません。
実際に不正がなくても、公務員の信用が低下する可能性があります。
こうしたリスクを避けるために、副業が制限されています。
2.本業に支障をきたす可能性があるため
公務員の仕事は、国民の生活や社会の安定に直結します。
そのため、「本業に支障をきたすような働き方」は避ける必要があります。
もし副業に力を入れすぎて、
- 残業や休日出勤ができなくなる
- 疲れがたまり、本業のパフォーマンスが低下する
- 副業のトラブルが本業に影響を与える
といったことが起きれば、公共サービスの質が落ちる可能性があります。
こうした理由から、公務員には「職務専念」の原則が求められ、副業が厳しく制限されています。
3.法律で明確に決まっているため
公務員の副業は、「国家公務員法」や「地方公務員法」によって厳しく制限されています。
特に関係するのが以下の2つのルールです。
【国家公務員の場合】
◯ 国家公務員法第103条
◯ 国家公務員法第104条
【地方公務員の場合】
●地方公務員法第38条
●地方公務員法第39条
この2つは、簡単にいうと
・営利目的の仕事(例:会社経営、アルバイトなど)を原則禁止。
・任命権者(上司)の許可なしに他の仕事禁止
としています。
つまり、これが法律で決められてしまっているので、副業は法律に違反することになってしまうというわけです。

法のもとには皆どうすることもできませんね・・
公務員の副業が制限される理由は、以下の3つです。
- 公務の公平性を守るため(誰かに有利にならないようにする)
- 本業に悪影響を及ぼさないため(公務最優先)
- 法律で禁止されているため(どうにもならない)

これだけの制限がある分、充実した福利厚生が用意されています。
公務員の副業解禁の流れと最近の動向
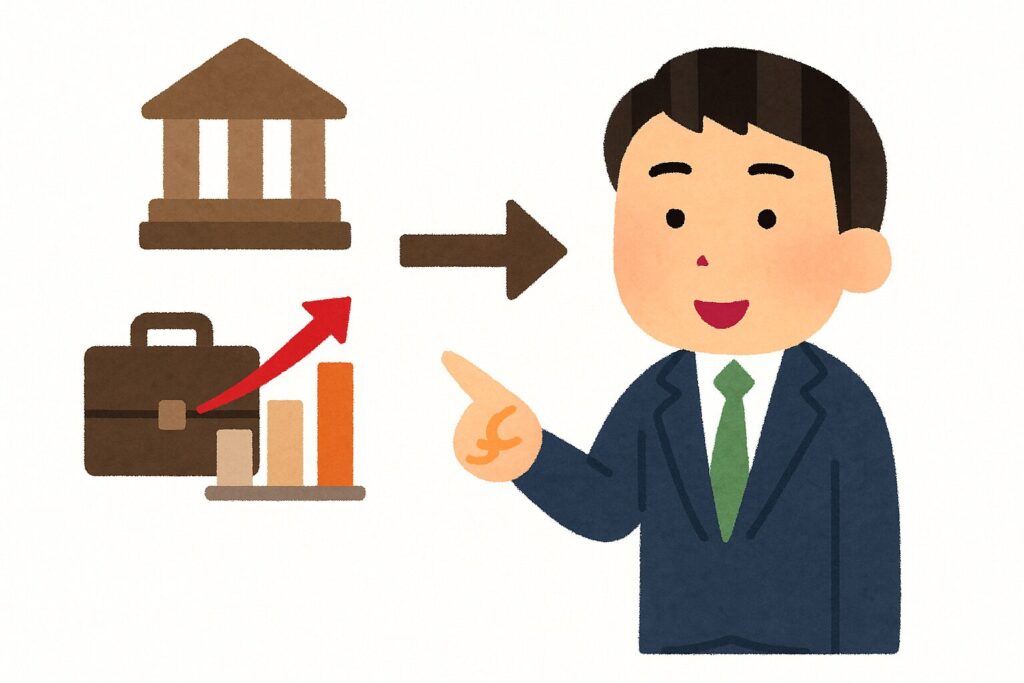
公務員の副業解禁は、近年注目を集めています。
国でも公務員の副業については議論されてきたところです。
ここでは、副業解禁の流れと最近の動向について、具体的な事例を交えて説明します。
一部の地方自治体で認められた副業
まず、公務員の副業が認められた具体的な事例を紹介します。
山形県新庄市(商業活性化支援)
新庄市の職員が地元NPO法人の理事長として、商店街活性化活動に従事。
「100円商店街」イベントの企画・開催:商店街全体を100円ショップに見立てるイベントで、年間50回程度の活動を実施。
週休日や年次有給休暇を利用して活動し。
月に約3万円の報酬を得る。
佐賀県佐賀市(障がい者支援)
佐賀市の職員が任意団体「○○な障がい者の会」の代表として、障がい者支援活動を行う。
ラジオ番組の制作と発信、障がい者交流事業(いきいきサロン)の実施。
週休日や年次有給休暇を使い、週2~3回の活動を実施。
月に約2万円の報酬を得る。
兼業の基準を明確化
これまで公務員の副業や兼業については、上長の許可を得ればOKでした。
しかし、具体的にどのような場合にどのような働き方がOKなのかという基準が曖昧でした。
そこで、一部の自治体において明確な基準を設けて積極的な利用を促しています。
例えば、神戸市では
「社会的課題の解決など、地域の発展や活性化に寄与するのであれば、神戸市内外問わず活動を許可。」
とし、現在須磨海岸での障害者支援や手話通訳など、社会貢献を目的とした様々な活動がおこなわれているようです。
これ以外にも
・奈良県生駒市
・長野県
・福井県
・茨城県笠間市
・北海道鹿部町
これらの自治体で兼業における認可基準を独自に定めています
いずれも「地域貢献と公益性が高いもの」を認可基準としています。
公務員も今後副業がどんどん解禁されるか?

先ほど解説した副業の事例を見ていると
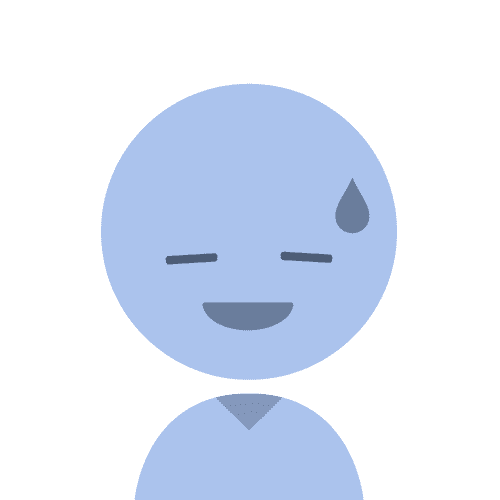
じわじわと副業の波が公務員にも押し寄せてきて、ゆくゆくはダブルワークも可能になってくるんじゃない?
と思いませんか?
ですが、私の答えは「NO」です。
今後ますます副業が解禁されるとしても、限定的なものとなるでしょう。
その理由を過去の経験からシンプルに挙げていきます。
兼業を許可する意図はあくまで「社会貢献」だから
おそらく多くの方が副業解禁といって期待しているのは
「収入を増やすために副業をする」
ことではないでしょうか。
しかし国が考える公務員の副業目的は違います。
「地域貢献と課題解決のために、公務員の知識と経験を活かした公益性の高い仕事に取り組むことを認める」
という意図です。
つまり営利を目的とした単純な副業を許可するわけではないということです。
また
①本業の能率が下がらない
②利害がぶつからない
③品位を損なわない
この3つをクリアできる副業ってすぐに思いつきますか?
正直、私には判断が難しいです。
そのため
【午後5時まで働いて、その後ウーバーイーツのダブルワーク】
→能率落ちる?
【休日にyoutube配信で広告収入】
→品位を損ねる?
【ブログ解説でアフィリエイト】
→勤務に関する情報漏洩の恐れあり?
といったように、色々リスクが気になってしまいます。
そのため、あからさまなものが公に認められることは、今後も可能性として低いと推察します。


実際に、兼業として許可されたものを見ていくと、公共の利益を目的としたものになっています。
今後、各自治体において兼業の受け止め方は緩和されるかもしれませんが、公務員としてできる副業は限定的でしょう。
兼業できるほどの余剰時間と人員がない
仮に兼業するとなると、土日や有給休暇を利用して行うわけですが、公務員が抱える職務によってはそのような時間を取ることは不可能です。

ましてや激務部署では土日返上で仕事をしている人もいるほどです
また、年間通じて有給休暇を使いきれない職員もたくさんいるのが実情です。
そのため、まず業務負担量を減らす必要があります。
しかし、近年は情報量の増加に対応しきれず、人手不足も相まって業務負担量が増加している自治体も存在しています。

もし、副業する時間があれば、家庭の時間を作ったり、自分自身を休めることを優先するでしょう。
本業が疎かになる人が増える可能性がある
やればやるほど収入が増える副業を認めたら、公務員として本来の業務とどちらを優先するでしょうか?

おそらく多くの人が副業を優先するかと・・・
むしろ、それは人の心理に基づく当然の判断です。
つまり、副業を何でも認めてしまうと制御が効かなくなってしまい、行政サービスが低下する恐れがあるということです。
そうなることを分かっていて、国がわざわざあらゆる副業を認めるとは考えにくいです。
【必見】公務員の収入増加に副業も時間も必要ない
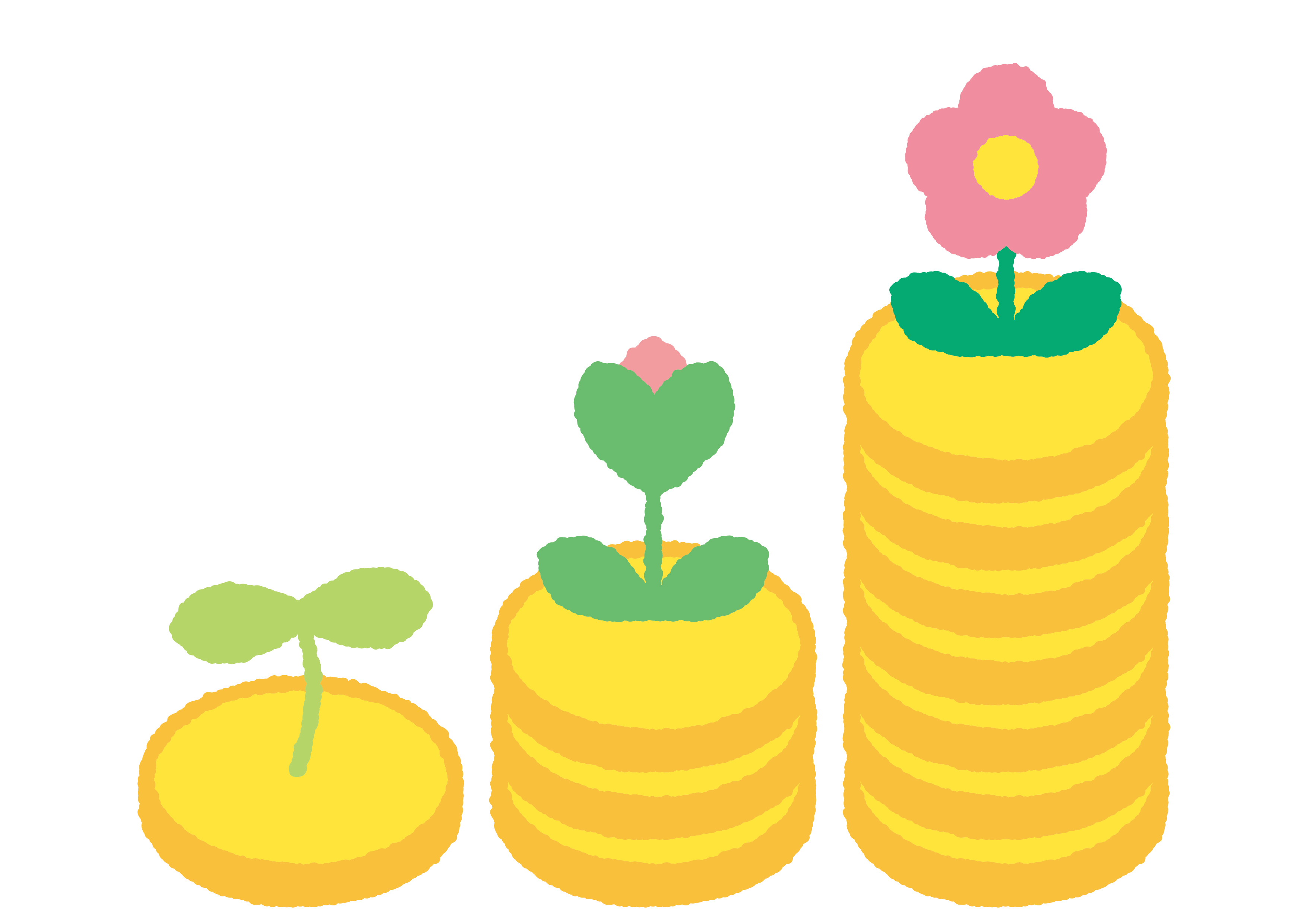
これまで挙げた公務員の副業に共通する特徴があります。
それは
「労働収入」
であるということです。
つまり、時間を切り売りして収入を増やすという方法です。

相応の時間が消費されるため、大幅な収入増加とはなりません。
一方で、一度仕組みを作ってしまえば自分が時間を掛けなくても、勝手に収益が見込める方法があるのをご存じですか?
それが資産を運用すること、すなわち「投資」です。
特に私がオススメするのは、
長期的に時間を掛けてお金にお金を増やしてもらう方法です。
これによって・・
・毎月の給料にプラスして余裕ができる
・わざわざリスクを冒して副業を選択しなくて良い
・自分が動かなくても勝手に増やしてくれる
など、多くのメリットが得られます。
また、公務員の安定した給与を活用した運用方法によって
リスクを抑えつつ資産を増やしていくことができます。
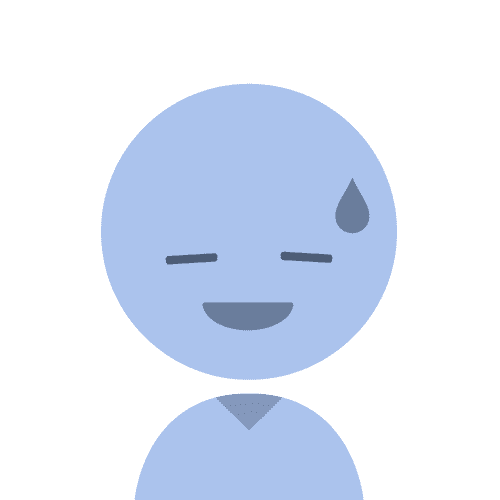
いやなんか投資って怪しいし、そんな簡単にお金は増やせんよ・・
実は、多くの方はそう思い込み「行動することを諦める理由」にしています。

実際に公務員時代何度もそういったセリフを聞いてきました・・
しかし、適切な方向性で知識と行動を起こせば、着実に資産を増やしていくことが可能です。
必要なのは、「知ること」と「動くこと」。
たったこの2点を実践し仕組みをつくってしまえば、収入や仕事量に不満を感じることなく、ストレスフリーの満たされた人生を送ることができるようになります。
興味のある方は無料のメール講座を実施しています。
【公務員の実情を深く理解し、資産を形成してきた私からの生きた情報】
をチェックしてみてください。
公務員特化の資産形成講座です
今メルマガ登録すると
「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」
を期間限定プレゼント!
(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)
※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。
※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。
※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。
※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。
公務員の副業は解禁というより制限【まとめ】

公務員の副業解禁について解説してきました。まとめると以下の通りです。
公務員の副業解禁の背景と現状
公務員の副業が解禁される背景には、職務に専念するための職責や公正な行政を行うための制約がある。
国民全体の利益を最優先に考え、営利目的の副業は禁止されている。
しかし、副業解禁の動きが進む中、一部の副業については促進されている。
一方で、特定の企業との関係が公正な判断を妨げる恐れがあるため、営利目的の副業は厳しく制限されている。
現在認められている副業の具体例
講演活動
公務員が専門知識を生かして行う講演は、許可を得ることで副業として認められている。
例:地域の防災講座。
執筆活動
専門分野に関する書籍や記事の執筆も、公務員の副業として認められる。
例:法律関係公務員の法律解説書の執筆。
小規模農業
自給を目的とした小規模農業も、副業として認められる場合がある。
例:相続した土地を外部に委託して成果物を受け取る。
いずれも内容や計画を詳細に提出し、勤務先からの承認を得ること。
副業解禁の流れと最近の動向
副業解禁の動きは、特定の自治体や機関で試行的に実施され、その結果を基に規制緩和が進められている。
一部地方自治体で、副業が認められた具体的な事例
・山形県新庄市の職員が地元NPO法人の理事長として商店街活性化活動に従事し、地域活性化に貢献。
・佐賀県佐賀市の職員が任意団体「○○な障がい者の会」の代表として障がい者支援活動を行う。
その他自治体でも兼業基準を明確化し、地域貢献を推進している。
今後の副業解禁の展望
公務員の知見を活かした地域貢献型の副業は推進しているが、営利目的の副業に関しては引き続き認められない可能性が高い。
職務専念や余剰時間の捻出等様々な課題がある。
現状では、副業を大幅に解禁するのは難しいと予想されます。
公務員のメイン収入としては引き続き給与収入になってしまいますが、これだとある程度生涯年収が決まってしまいます。
つまり、あなたの使えるお金も決まっているということです。
これを変えたいのであれば、早い段階で運用に思考を切り替えていくことが重要です。
率直にお伝えすると、絶対に成功する投資は存在しません。
100%成功を謳っているとしたら、それは詐欺案件です。

ですが、私も実践してきた限りなくリスクを抑えた堅実な投資方法はあります。
詳細はメール講座でお伝えしていますので、
・たまに旅行や食事で贅沢したい
・欲しいモノを我慢したくない
・経済的なゆとりを手に入れたい
こういった思いがあるなら、いますぐに一歩を踏み出しましょう。
同じ公務員。なのに差が付く
今メルマガ登録すると
「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」
を期間限定プレゼント!
(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)
※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。
※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。
※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。
※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。