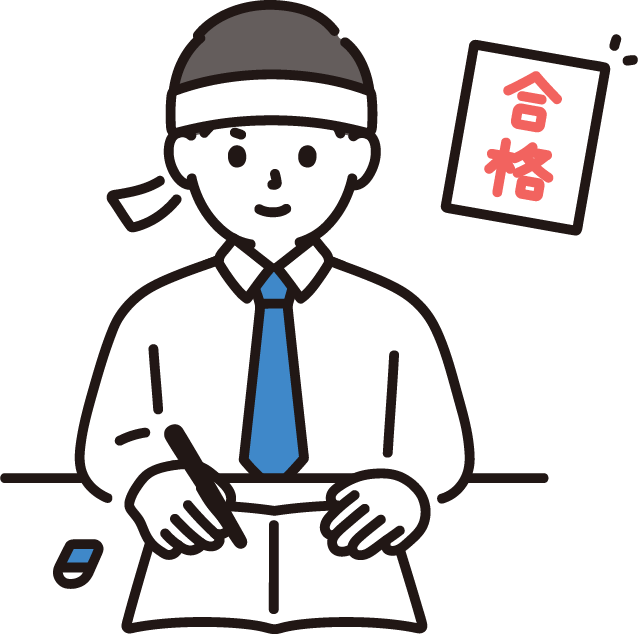公務員の有給休暇事情【何日取れるか元公務員が解説】

公務員として働く際、休暇制度は生活の質に大きな影響を及ぼします。
しかし、一般的に公務員の休暇についての情報は限られており、具体的な取得方法や制度を知ることは難しいことが多いです。
「公務員の休暇は何日取得できるの?」
「休暇の種類はどんなものがあるの?」
など、気になりませんか?
実際に私も公務員として勤務していた時に、どのような種類の休暇があるのか把握しておらず、毎回人事担当に相談しているような状態で、自分の権利には疎かったです。
公務員の年次休暇や特別休暇等について詳しく知っておくことは、現役公務員や公務員になりたい方々にとって非常に重要です。

自分の権利を知らずに働いていると、思わぬ損をしてしまうこともあります
結論として、
・年次休暇は1年で20日
・特別休暇は状況に応じて数日
・有給の病気休暇90日
・別途手当金支給の休職制度
・同じく育児休業制度
と、盛りだくさんになっています。
しかし、実際に全部取得しきれるのかというと、正直難しい事情もあります
公務員の有給休暇事情について、本記事で具体的に解説していきます。
ちなみに、私も公務員として過去20年間勤務してきた中で、様々な休暇を取得してきました。

公務員が取得できる休暇の豊富さは目を見張るものがあります。
そんな私だからこそお伝えできる情報を網羅していきます。
現役公務員はこれを基に、無駄のない休暇を取得して充実した公務員LIFEを送りましょう。
公務員の年次(有給)休暇は何日取れる?

公務員は有給休暇を「年次休暇」と呼び、よく年休などと呼ばれることが多いです。
休暇の付与日は年度(4/1)であったり、1/1であったりと自治体によって異なるのでご注意ください。
年次休暇の付与日数と取得状況について詳しく見ていきましょう。
年次(有給)休暇は1年20日付与、繰越上限40日
フルタイム公務員の有給休暇は、一般的に年間最大20日が付与され、1日を7時間45分でカウントされています。
会計年度職員等は採用月日によって変わり、最大20日から経過月数を減じる形です。
1時間単位で取得可能で、私の自治体では分単位の端数は繰り上げになっていました。
※1時間30分=2時間の休暇申請
自治体によって若干の違いはありますが、概ね国の規定に準じた形で、公務員のワークライフバランスをサポートしています。
ちなみに年次休暇に取得理由は必要なく、自分の為に取得できる休暇です。

とはいえ、さすがに行政サービスに支障をきたしてはマズイので、各々で仕事の区切りをつけて取得していることが多いです。
また、有給休暇の繰越上限が40日と設定されているため、公務員は未使用の休暇を上限まで次の年に持ち越すことができます。
(例)
・残日数30日(繰越20日)
・翌年20日付与
→新年次休暇40日(上限)
公務員1年目は何日取得できる?
新規採用された公務員は、採用されてすぐ年次休暇を取得できるのか気になりますよね。

急遽私用で休みをもらいたい時もあるはず・・
ズバリ、新規採用の公務員でも休暇は取得できます。
ただし、取得できる日数については自治体による切替年度によって違いがあります。
なぜなら、新規採用の公務員は4月1日付採用ですが・・
1/1年次休暇切替の場合・・15日
4/1年次休暇切替の場合・・20日
と、切り替えるタイミングによって日数が変わるためです。
例えば、1/1切替の場合は、当初から20日間の有給休暇を完全に利用できるわけではありませんが、翌年1/1から新たに20日が付与されます。
一方で、4/1切替の場合は20日間フルに取得できますが、翌年4/1まで付与されない為、計画的に利用していく必要があります。

どちらも一長一短あります
※非常勤採用はまた別途定められています。
20日間の年次休暇は全て消化可能?
さて、仮に年次有給休暇が20日与えられたとしたら、この休暇をすべて消化していきたいところです。
ですが、自治体の実情によっては、難しいです。
なぜなら、休みたくても業務量次第で休めないためです。
実際に、令和2年度の総務省による年次休暇取得平均を示してみました。
| 区分 | 平均取得日数 |
| 都道府県 | 11.8日 |
| 指定都市 | 14.0日 |
| 市区町村 | 11.1日 |
~令和2年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要~ より

平均で5日以上取得できていない状況ですね・・

全自治体でも20日を全部消化するのは難しい状況が伺えます。
ただ、配置される部署によっても取得しやすさは違ってきますが・・
公務員の業務は、時折予測不能な状況に直面することが多く、長期休暇を取得することが困難である場合があります。
例えば
・国から降りてくる至急の依頼や調査
・災害時の避難所の設立や住民の安全確保
・議会対応 etc..
このように、権利上と実態とで異なる場合があることに注意が必要です。

2~3週間に1回1日分の年次休暇を取得するのは、不可能ではありませんが、かなり積極的に取得しなければなりません。
しかしながら、時代的には休暇を取得しやすい職場環境づくりを国が進めています。
今後、ワークライフバランスの観点から更に取得日数が増えてくる可能性はあります。
・1年目から15or20日分取得可能
・全体平均は11日程度。全部消化は難しい
・翌年に最大40日まで繰り越し可能
【意外に知らない】公務員の有給特別休暇

年次休暇以外にも有給の特別休暇が公務員には用意されています。
年次休暇で処理も可能ですが、取得要件を満たしている場合には特別休暇を利用することで、年次休暇を温存できます。
どのようなものがある?特別休暇の種類
公務員の有給の特別休暇はさまざまな種類があります。
よく使われる休暇を以下に挙げてみました。
・災害に対処するための災害時特別休暇
・結婚や出産に関連する特別休暇
・子供の看護に伴う特別休暇
・家族や親族の死亡に伴う葬儀特別休暇
・夏季特別休暇
・特定の疾病に対する特別休暇
etc..
さらに、時代の変化に合わせてどんどん新しい特別休暇が創設されています。

年次休暇に加えて、これらの休暇があるのはありがたい事ですね
これらの休暇のポイントは、個々の状況に応じて取得でき、年次休暇を消費せずに有給で取得できること。
自治体によって、その他にも特別休暇が存在する場合もありますので、人事担当や管理職に相談してみることをオススメします。
特別休暇の取得状況は?
年次休暇と変わらず、特別休暇の取得状況も部署の状況や組織の人員に依存します。
つまり、忙しい部署や人が少ない自治体だと、取得日数が少ない傾向にあります。
参考までに私の所属してきた部署の例を挙げます。
・結婚休暇・・ほぼ取得していた
・忌引・・・・1~3日程度取得していた
・看護休暇・・必要に応じ取得していた

全体的に休暇に関しては寛容な所属ではあったと思いますが、それでも年次休暇は10日間取っていたかどうか・・といった所です。
これはあくまで一例であって、具体的な取得状況は、組織によってかなり異なります。
また、部署だけでなく、自分の職務や地位、勤務期間によっても変化する可能性があります。
特に、管理職相当の地位にある職員は、何かあった時に判断しなければならないので、取得日数は少ない傾向です。
特別休暇を取得するためには、事前に自身の組織の規則を確認し、あらかじめ上司と調整すると良いでしょう。
実は「無給」の特別休暇もあります
無給の特別休暇とはその名の通り、給料は出ないが、休暇として認めている状況です。
これは、有給休暇ではカバーできない特定の状況や、目的に対応するための選択肢です。
例えば、
・長期の家族介護休暇や
・特定職務に専念するための配偶者同行休暇
が該当します。

これは私の経験上では、レアな事例ですね・・
これらの休暇は、公務員がライフイベントや個人的な目標に対処するための、弾力的な選択肢として家庭生活を考慮したものです。
無給ですので給料は出ませんが、状況に応じて共済組合からの手当金や、ボーナスも満額ではないにせよ、支給対象になります。
このように、無給の特別休暇は長期間取得できて非常に魅力的な休暇制度ですが、デメリットもあります。
それは、有給の休暇比べると、申請と承認が非常に煩雑になる点です。
事前にしっかりと管理職や人事部と相談し、連携を図って利用するようにしましょう。
〇有給の特別休暇
・夏季休暇
・結婚休暇
・看護休暇
〇無給の特別休暇(わりとレア)
・配偶者による海外研修同行休暇
・家族の介護休暇
療養(病気治療)も有給で取得できます

年次休暇、特別休暇に加えて、さらに有給の休暇制度があります。
それは、疾病療養を目的とした「病気療養休暇」です。
有給ではありますが、取得日数によって昇給やボーナスに影響があり、年次休暇や、特別休暇とはまた異なるので、具体的に解説していきます。
90日間は有給で取得可能
公務員には病気や健康上の理由による休暇が用意されており、最大で90日間の療養休暇を有給で取得できます。
また、病気の種類は、肉体的・精神的な疾病の両方が対象で、取得要件もわりと広いです。

例えば骨折をしてしまい、病院に通院しなければならないなどの場合も、短期間の療養休暇が取得できます
ただし、長期の療養休暇については自己申告というわけにはいきません。
承認には、医師の診断書等で病名と治療期間を証明する必要があります。

疾病の治療には時間を要する場合が多いため、病気療養休暇は公務員の身体的健康とメンタルヘルスを保つための恵まれた制度です。
特に、有給かつ長期で取得可能というのが大きなポイントです。
病気療養休暇は、公務員として勤める者にとって経済的にも心強い制度です。
期間によってボーナスや昇給等に影響あり
長期にわたる療養休暇を取得する場合、ボーナスに一部影響を及ぼすことがあります。
この影響は取得日数によって異なりますが、長くなるほどボーナスの支給が減額される可能性があります。

しかし、実際には休養しているわけですから、その中である程度ボーナスが支給されるというのは優遇されているともいえますね
また、定期昇給にも影響があります。
なぜなら、昇給の算定には1年間通した勤務成績が基準となるためです。
つまり、休暇が長いと「良好な勤務成績」とはならないということです。
結果として、一部昇給が抑制されたり、昇給が次年度以降に繰り越されるといった措置になることもあります。

90日の休暇で復帰できなければ「休職」
療養休暇の最大期間は90日間であり、この期間内に思うように回復できなかった場合にはどうなるのでしょうか?
結論「休職」を申請する形になります。
休職は最大3年間公務員の雇用状態を一時的に停止させ、その間に回復を図るための制度となっています。
なお、休職して1年間は80%の給与が支給されます。
ボーナスは算定期間が半年と長い為、在職期間中であった初回の分が、支給される可能性があります。
2年目以降給与は支給停止しますが、その後も休職する場合には、管轄の共済組合より手当金が毎月支給されます。

実質収入が途絶えることは無いんですね・・・
なお、長期の休職中には代わりの職員が補充される場合もあります。

補充はパートだったりフルタイムだったり様々。希望者次第です。
このように公務員の病気療養には手厚い復帰制度が用意されています。
公務員であれば申請できる権利があるので、いざという時のために覚えておきましょう。
・最大90日取得可能
・給与は通常支給
・ボーナスは取得期間によって影響あり
・定期昇給は取得期間によって影響あり
※自治体によって若干異なる
・3年間取得可能
・1年目は80%給与支給
・2~3年目は給与ナシ。かわりに手当金が給与の2/3程度支給
・ボーナスは休暇期間によって影響あり
・定期昇給は休暇期間によって影響あり
※自治体によって若干異なる
育児休業も3年間あります

休暇ではなく、お子さんの育児に専念できる休業も存在します。
休業期間は1人のお子さんにつき最大約3年。
今は女性だけでなく、男性も積極的に取得するよう国が呼びかけており、以前よりも取得しやすい状況が生まれています。
育児休業中の給与はナシ
公務員は育児休業を最大3年間まで取得できるため、仕事と家庭を両立しやすいです。
しかし、育児休業中には通常の給与は支給されません。
また、ボーナスは育児休業の期間に応じて減額され、やがて支給されなくなります。

代わりに育児休業手当金が支給されますのでご安心ください
算定方法は自治体によりますが、ボーナスの算定期間は半年と長い為、育児休業を取得した最初のボーナスは一部支給されることがあります。
さらに復帰した後も、育児休業中と復帰後で算定期間をはさむので、初回のボーナス支給日には減額されている場合があります。
育児休業は通常の休暇とは異なり、休みの形態や申請方法も異なります。
取得する際は、家庭の経済状況なども十分に考慮し、管理職と相談しましょう。
給与の代わりに育児休業手当金が支給される
育児休業中、公務員としての給与はゼロ。

さすがにお子さんが生まれた中で無給状態は厳しいですよね・・
ですが、その代わりに共済組合による育児休業手当金が支給されます。
この手当金は、子が1歳になるまでの期間において給与の約2/3程度支給してくれるもの。
育児休業期間中の生計費をサポートし、家計への負担を軽減してくれる制度です。

とはいえボーナスもなく、年収でいうと結構なダウンになるので、支出は慎重に・・
収入と支出のバランスをよく考えて、休業期間を過ごす必要があります。
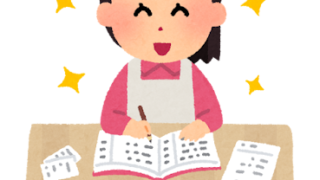
休暇の取得は人事担当に相談しよう

休暇の取得方法や適切な休暇の選択は、公務員にとって重要です。
なぜなら、この選択次第によっては、給与支給の有無にかかわってくるからです。
そして、公務員がどのような休暇を使うか検討する際、管理職や人事部門との協力は不可欠です。
連携の重要性について元公務員的な視点から解説します。
休暇の選択肢が幅広く自分ではわからない部分もある
これまで示したように公務員の休暇にはさまざまな種類があります。
有給休暇、特別休暇、療養休暇、育児休業・・
それぞれの休暇には異なる要件と制約があり、自分ひとりで選択することは困難です。

例えば、有給休暇と療養休暇は取得可能日数が異なりますが、この間に昇給やボーナスの支給制限があったり、申請の方法が変わってきたりします。
管理職や人事部門は、こういった服務面において非常に豊富な知識を持っています。
状況に応じた休暇の違いを説明してくれ、自分が最適な休暇の選択を行う際に役立ちます。
休暇に関する法的知識を得られる
休暇には法的な要件が存在し、公務員の権利と責務を規定しています。
例えば、有給休暇は年間20日が最低保証され、最大40日まで繰越できるというのは、条例などで決められた根拠があります。
さらに特別休暇は、覚えられないくらいに非常に多くの事例に対応しており、条件によって必要日数分取得できます。
管理職や人事部門はこれらの関連法令に基づき、年次休暇の残日数等を含め公務員における権利について適切なアドバイスをくれます。

自分が分からないことは、ササっと聞いてしまった方が良いですね

人事を司る側としても、あらかじめ相談がある方が、いざ取得してもらう際にもスムーズです
休暇の計画と仕事の割振で抜けた後の対応をスムーズに
休暇を申請することは、組織運営に影響を及ぼします。
特に長期休暇の場合、業務体制を見直し、休暇取得以降も適切な運営を確保する必要があります。
管理職と協力して休暇の始期や取得期間について計画を立て、他の同僚に負担がかからないように配慮することが重要です。

特に、小さい部署ではひとりひとりの負担が大きくなりがちです。引継ぎなどもあらかじめ行っておくことをオススメします
周囲との連携をはかりつつ公務員の権利を行使しよう
2021年度に心の不調等で1カ月以上の病気休暇および休職した地方公務員は、全国で3万8467人。
これは全体の約1.2%に相当していることが総務省の調査で判明しています。

100人に1人・・。こう見ると決して少ないとは言えませんが、多いとも言い難い数字ですね。
そもそも病気休暇などは実はそこまで多いものではなく、組織の中でも特別な事案に該当します。
そのため、周りの同僚に相談しても、明確な答えが得られないことがあります。
また、健康状態を理由に休暇を取得する場合、段階を踏んであらかじめ申請して取得できるとは限りません。
突発的な理由で出勤不可能になってしまった場合、行政サービスが低下しないよう組織として迅速な措置を講じる必要があります。
そのため、あらかじめ管理職や人事部門とは風通しを良くしておくことで、適切なタイミングでの休暇となるよう調整を図ることが出来ます。
管理職や人事部門との協力は、公務員が休暇を取得している間も組織が効果的に運営されるために重要。
周囲の協力があって公務員のワークライフバランスが機能し、組織全体が円滑に運営されることを忘れてはいけない。
【休暇取得×お金の不安解消】で思い切り休める
有給休暇や特別休暇、育児休業など、公務員ならではの充実した休暇制度。
ですがその一方で、その間の収入や将来の資産形成に不安を感じることはありませんか?
・育児休業手当金だけで乗り切れるか不安・・
・病気休暇が長引くほど入院や通院費用がかさむ
・長期で休みたいけど、収入が減るのは困るから短縮せざるを得ない
実はこれらの根源は全て「経済的不安」からきています。
その結果、充実した制度があるのにも関わらず、お金の不安によって無意識に選択肢が狭められてしまっている状況が生まれています。

コレ、実は多くの人が無意識にやっていることなんです・・
そこで、解決策とまではいきませんが、オススメしたいことが1つあります。
それは、
【家計の洗い出しと見直し】
です。
なぜなら、収入に対して適切な支出を分析することで、家計を改善させ安定させることができるためです。
具体的には、国家資格を持つFPにお金のあらゆる悩みを相談し解消させること。

私がオススメするのはマネプロ一択
お金の専門家であるFPに相談することで
・育児休業中も無駄な支出を抑え、将来へ備えられる
・病気休暇や特別休暇中でも、精神的余裕を持って生活できる
・休暇期間だけでなく長期的なライフプランが見通せる
など安心できる資産計画によって、休暇中は家族や自分の時間を存分に専念できます。

これは理想的な休暇のとり方ですね!
なかでも、マネプロのFPは福利厚生の制度にも精通しており。あなたの立場や生活に合った提案を行ってくれます。
【マネプロのオススメポイント】
・相談実績は全国で15万人以上
・満足度は98.9%
・完全無料で、無理な勧誘は一切なし
・オンラインでどこでも相談可能
・相談回数は無制限
など、安心して利用できる環境が整っています。
万が一、相談内容に満足できなくても場合は、掛かった費用はナシ。
特にあなたのデメリットはありません。
モヤモヤした経済的不安を解消し、あなたの人生をもう一段階豊かにするためにも、一度は相談してみる価値はあります。
【無料】相談しない理由ナシ!
お金の悩みは専門家へ
「自分にとっての最適なマネープランは?」
金融資産に精通した国家資格を持つFPにおまかせ!
将来の大切なお金の不安を「無料」でまとめて解決しましょう。
※相談は場所を選ばずオンラインで手軽に参加できます
公務員の有給休暇は色々ある【まとめ】

公務員の年次(有給)休暇・休業に関する情報をまとめます。
繰り返しになりますが、自治体によって若干対応が異なります。しっかりと自分の所属において確認をしましょう。
※基本は国の規程に準じているので、大きく異なるということはありません。
年次休暇の付与日数と取得方法
公務員は有給休暇を「年次休暇」と呼び、一般的に20日が年間最大付与。
これは1日を7時間45分で計算し、1時間単位で取得が可能。
年次休暇の取得状況
20日間の年次休暇を全て消化することは難しく、実際の取得日数は部署や業務によって異なる。
これは災害や緊急事態への対応、急な業務要求によるもので、長期休暇の取得が難しい場合もある。
新入公務員の年次休暇取得
新規採用公務員の取得可能な年次休暇は、採用時期によって異なります。
例:4月1日年次休暇切替の場合・・20日間の有給休暇が利用可能。
1月1日年次休暇切替の場合・・15日間の有給休暇が利用可能。
特別休暇の種類と取得状況
年次休暇以外にも有給の特別休暇が公務員には用意されている。
例:子の看護、結婚や出産、葬儀等
特別休暇は年次休暇を消費せずに取得でき、取得状況は部署や個人の状況に依存する。
無給の特別休暇
無給の特別休暇は、給与は出ないが、特別な状況や目的に対処するための選択肢。
例:長期の家族介護、配偶者の海外研修同行等
療養(病気)休暇
公務員は療養休暇を利用して、肉体的および精神的な疾患の治療に専念できる。
最大で90日間まで取得可能。
長期の療養休暇を取得する場合、ボーナスや昇給に一部影響がある。
休職
90日の療養休暇以降でも3年間の休職が選択可能。
1年目は80%の給与支給
2年目以降は無給に代わり休職手当金が給与の2/3程度支給される
育児休業
公務員には育児休業は、1人の子供につき最大3年間取得可能。
母と父どちらも取得可能。
期間中給与は支給されず、代わりに育児休業手当金が1歳までの間、給与の2/3程度支給される。
管理職と人事部門は連携・協力を図ろう
休暇の取得方法や選択肢は多様で、取得要件もさまざま。
管理職や人事部門との相談はこの情報を知ることができ、公務員が最適な休暇選択を行うのに役立つ。
休暇取得計画や業務の割り振りについても周囲の協力が必要で、休暇後の適切な対応について引継ぎを行っておくこと。
このように見ると休暇面では公務員はしっかりと体制が整っており、非常に恵まれています。
しかし、恵まれているにもかかわらず、十分に制度を活かしきれていない実情もあります。
なぜなら、要因の1つに経済的な不安があるからです。
実際に、お金が不安だからという理由で休業期間を短縮する事例も見られています。
そのため、根底にある経済的な不安を、家計の見直しを図ることで解消し、公務員の権利を最大限行使していきましょう。
・相談実績は全国で15万人以上
・満足度は98.9%
・完全無料で、無理な勧誘は一切なし
・オンラインでどこでも相談可能
・相談回数は無制限
と、圧倒的なサービス内容を無料で受けられるマネプロをオススメしています。
気になる方はチェックして明日以降の豊かな人生につなげてみてください。
【無料】人生をより豊かに
お金の悩みをスッキリ解消
金融資産に精通した国家資格を持つFPにおまかせ!
将来の大切なお金の不安を「無料」でまとめて解決しましょう。
※相談は場所を選ばずオンラインで手軽に参加できます