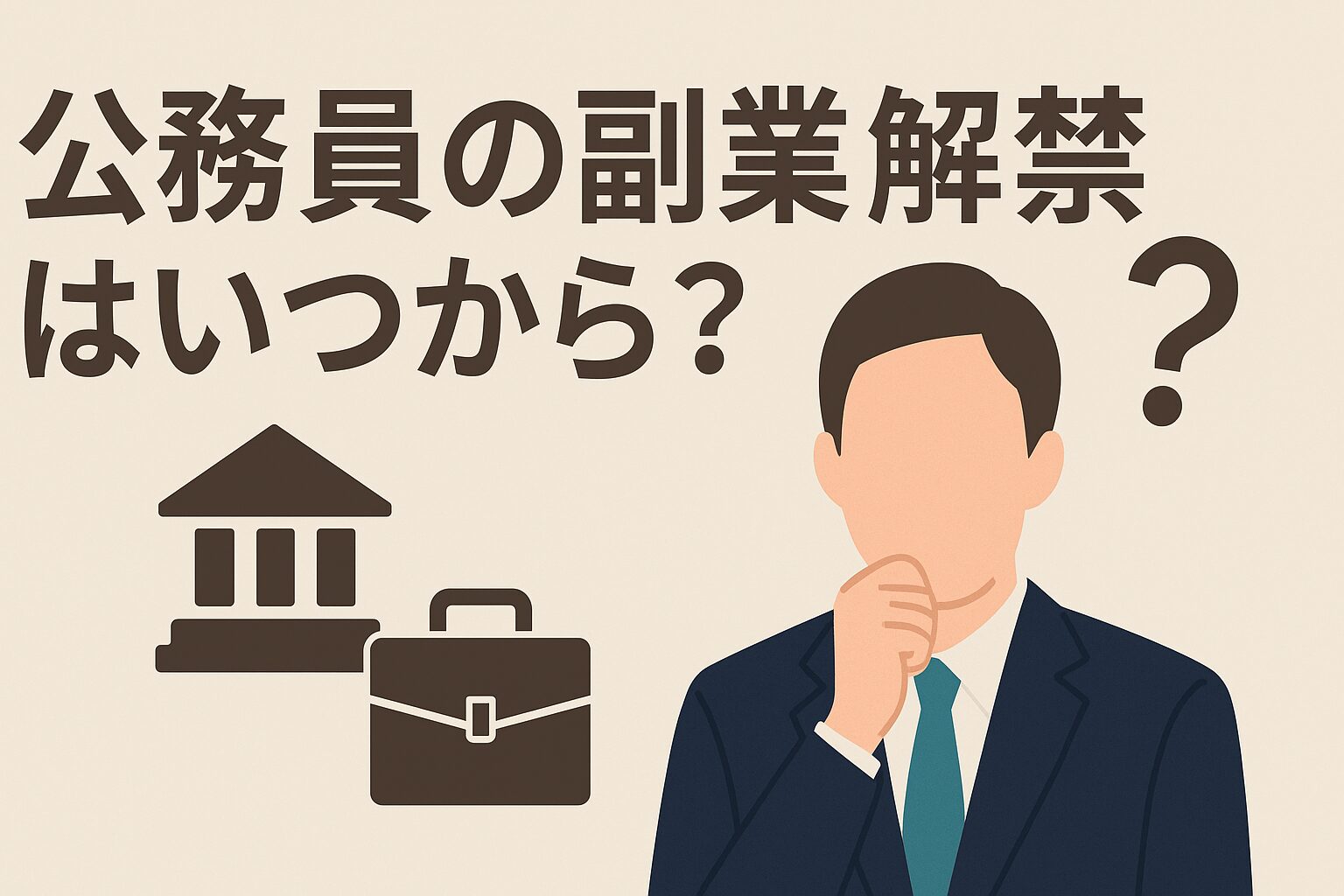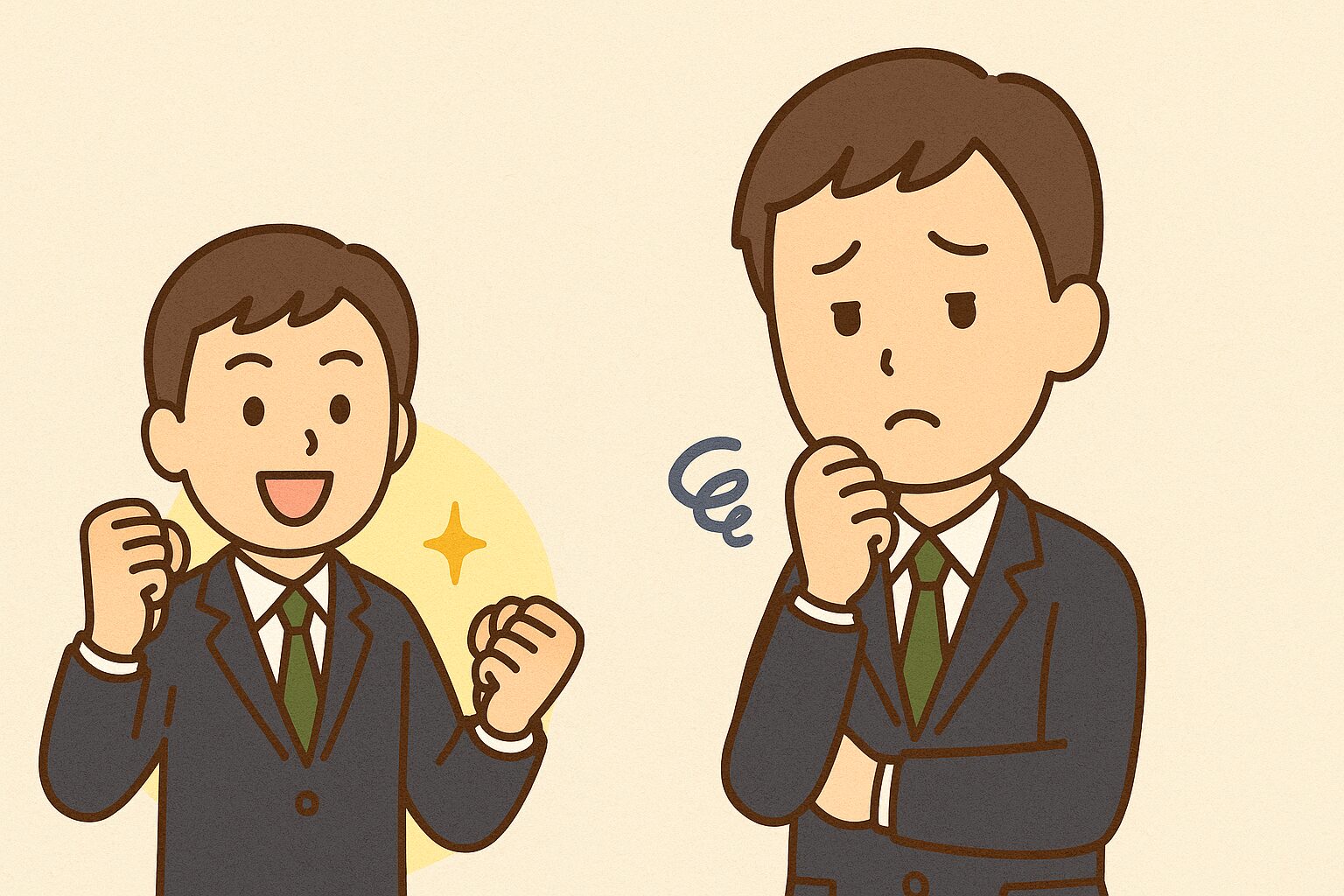公務員のサービス残業(サビ残)は違法?【元職員が実態を解説】

「他の職員はどのくらい残業代をもらっているんだろう…」
「定時を超えて働いているけど、ちゃんと手当は働いた分出るのかな?」
「公務員のサービス残業って違法では?実態が知りたい」
こんな疑問を抱えていませんか?
私も公務員として働いていましたが、業務の多さから残業が割と多いこともあり、他の人の様子が気になっていました。

アレ、残業代って全部請求できないの・・?って衝撃を受けました。
まず、結論から簡単に説明すると、特に忙しい部署や職種では、残業は頻繁にあります。
しかし、その残業時間分を全て請求することはできず、結果としてサービス残業となってしまっていることもあります。
なぜそうなってしまうのか、本記事で詳しく解説していきます。
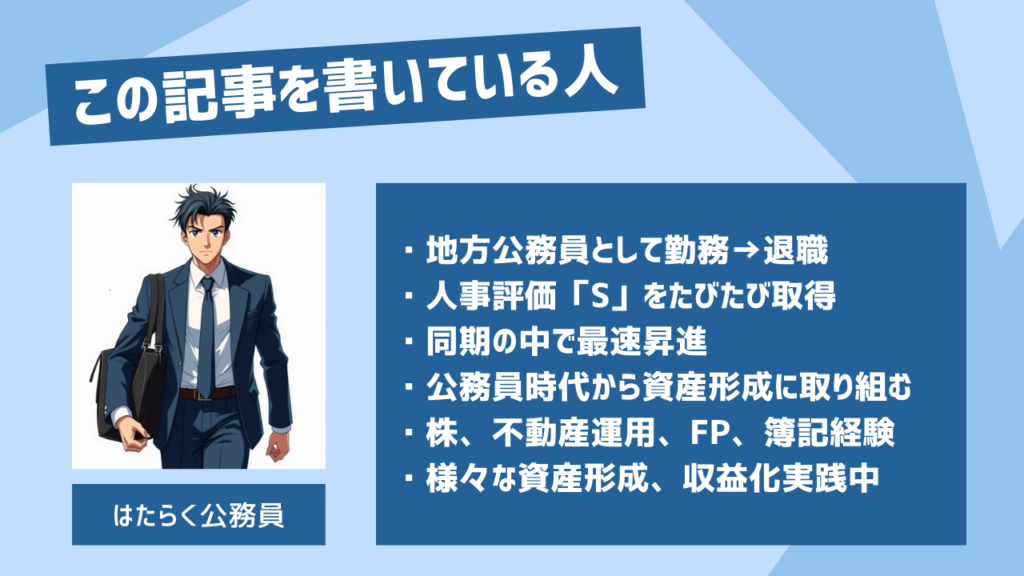
→ド素人だった自分でもゼロから着実に資産形成できたノウハウはコチラ
私自身、公務員として勤務してきましたが、組織として経験してきた現場のリアルもお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
公務員のサービス残業(サビ残)のリアルな現状
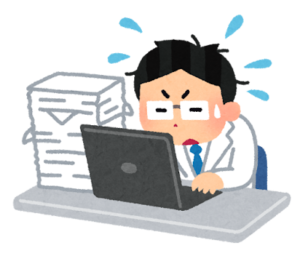
サービス残業は本当にあるのか?
公務員の中には
「定時で帰れてサービス残業なんて存在しない」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、実態は違います。
なぜなら、繁忙期もあり、そう簡単に割り切って働くことができない場合もあるからです。
実際に、多くの公務員が定時を超えても働いているにもかかわらず、ある一定以上の勤務については、適切な残業代が支払われていないケースが多数あります。

もちろん、本来は払ってもらうべきなんですが・・・諸事情がありますね
特に、忙しい部署では、上司の指示でなくとも、仕事が終わらないため、自主的な「サービス残業」が発生することが多いです。
なぜサービス残業が起きてしまうのか、簡単にまとめると以下の通りです。
・人手不足
職種や部署ごとに業務に偏りがあり、職員数が限られているため、業務が回らない
・暗黙の風潮
正式に残業を指示されないが、仕事を終わらせるために仕方なく残業する
・連帯で業務を負担する
1つの業務を複数の職員でこなす場合があり、他の職員が残業していると、自分も帰りにくい
こうした理由から、サービス残業は公務員の世界でも日常的に行われています。

正式な残業の命令や承認がないために、手当が発生せず、そのままになっていることが多いのが実情です。
多忙な部署の超過勤務(サービス残業)の実態
特に忙しい部署や業務量が多い職種では、超過勤務が常態化しています。
例えば、福祉や財務、医療関連、警察などの現場では、常に多くの業務が発生し、職員一人あたりの負担が大きくなりがちです。
休日出勤という名の、お金が一切発生しないサービス残業も多数あります。
市役所での激務部署についてはコチラの記事で解説しています↓↓

このような部署では、時間外の労働時間が月100時間を超えることも珍しくありません。
そのため、肉体や精神共に強靭な人でなければ、長期の療養休暇に入ってしまう人もいます。
こうした過酷な状況下でも、残業代が全て支払われることは少なく、結果的にサービス残業がおこなわれています。
- 休日出勤:業務量が膨大で、通常の勤務時間内で仕事が終わらない
- 緊急対応:予定外の対応が発生することが多く、結果的に残業が増える
- 精神的な負担:常に忙しい環境で働くことで、疲労やストレスが蓄積されやすい
サビ残は違法?労働基準法と公務員の関係

残業代が出ない中で勤務することは違反ではないのでしょうか。
労働基準法と含めて公務員のサービス残業について解説していきます。
公務員に労働基準法は適用されない
ズバリ、サービス残業そのものは違法です。
具体的には、労働基準法第37条に違反する行為であり、労働基準法第37条に違反した会社には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰が科せられることもあります。
しかし、公務員は一般の労働者とは異なり、一部を除き労働基準法の対象外です。

労働基準法は民間企業の労働者を守るための法律ですが、公務員には「職務の特殊性」があるため、すべての項目が適用されません
たとえば、災害対応や緊急事態における職務では、時間外労働が発生することが多く、その際には労働基準法の規制に縛られないケースが見受けられます。
公務員法で労働に関する規定がある
労働基準法の代わりに、国家公務員法もしくは地方公務員法によって、公務員にも労働時間や休暇に関する法律や規則があります。
公務員の残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間と定められています。
忙しい部署などでは、月100時間未満・年720時間と定める場合もあります。
これは人事院規則によるもので、地方公務員もこの規定に準ずるようになっています。

ただし、これは残業時間の規定であり、残業代の支給に関する問題とは別です。
多くの自治体では、上限いっぱいまで残業代を確保するのは、予算の事情から難しいです。
そのため、実残業時間と残業代請求時間に乖離が生じ、これがサービス残業の正体になります。
残りは自主的な活動扱いなので、違法と言うわけでもないわけです。
公務員の残業代(時間外勤務手当)に関する記事はコチラでご覧ください↓↓

サービス残業に対する告発の方法とリスク
告発というと表現が強いですが、サービス残業の実態を知り、人事院や人事委員会に相談するという手段もあります。
しかし、それにはある程度のリスクも伴います。
なぜなら、公務員の組織のサービス残業は古くから常態化されており、そう簡単に変えられる問題ではないからです。
実際、私も含め多くの職員が同じ道を通ってきています。
つまり、狭い公務員の世界で、どうしもならない分かり切った事をあえて荒立てることで、
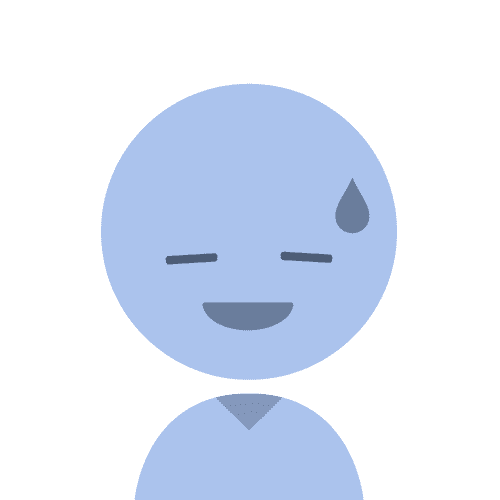
「面倒な問題を持ち込む奴・・」
「通常業務で手一杯でそれどころではないのに厄介・・」
といった自分の立場に何かしらネガティブな影響を与える可能性もあります。

けっして声を挙げることが悪いことではありません。

個人ではどうにもならないことを、あえて問題提起するのはいかがなものか・・というような雰囲気があるということでしょうか。
サービス残業問題に突っ込みすぎると・・・
- 上層部の注目を浴びる:騒ぎすぎることで、自分の評価が変わる可能性
- 職場の人間関係:職場内での扱いが変わるリスク
- 変化を望めない:無い袖は振れないので、徒労に終わる
このように人事部門に告発する際は、慎重に検討する必要があります。
そのため、なかなか難しい問題であると理解し、波風を立てずに粛々と業務をこなしている公務員も少なくないのが現状です。
【サービス残業体験談】100時間→10時間!?

サービス残業が当たり前だった当時の現場
私自身、多忙を極める時期があり、毎月100時間を超える残業をしていましたが、実際に請求したのは、そのうちの1/10にあたる10時間分だけでした。
なぜなら、正直に残業時間の報告をしてしまうと、残業に対しての報告業務という、とても余計な仕事が増えて面倒になるからです。
実際、当時の同僚も同じようなことをしており、おそらく多くの公務員が直面している現実です。
つまり、忙しい部署では定時を超えても仕事が終わらないため、サービス残業が常態化。
予算や報告業務の問題から、上司からは正式な命令等はなく、自主的に働くという扱いが多くあります。
勤怠管理システムは導入していますが、残業時間が月80時間を超えると、産業医との面談や、報告書を提出する必要があります。
そのため、意図的に残業時間を調整することもあります。

もちろん、記録に残すわけにはいきませんので、様々な方法で残業記録を回避します
また、公務員を志望する人は、真面目で責任感も強いため、残業代云々よりも自分の業務が片付くことを最優先してしまいがちです。
このような状況で、残業を申告しないまま仕事を終えることが日常的に行われています。
残業には予算の都合と業務合理性が必要
当時、残業代を請求する際には、いくつか注意点がありました。
1つは予算の問題。
例えば年360時間が残業上限だとして、まるまる残業代として請求している人は、そうそういません。
なぜなら、残業代も無限に支給できるものではなく、おおよそ決められた予算内で執行するという問題があるからです。

財源は税金ですからね。無駄遣いはダメなのはもちろんのこと、効果的に執行していく必要があるんですよね。
厳密には請求すること自体は可能ですが、その後、突出して残業時間が多い職員は、業務の改善策を厳しく求められるでしょう。
つまり、後々自分を苦しめてしまうことになるわけです。
2つ目は業務の合理性の問題。
時間外勤務を命令し、事後に承認するのは、所属長です。
その際に、当該業務に対して残業の合理性が無ければ、時間外勤務は認められません。
例えば、
「本来であれば勤務時間内に終わるような通常業務の内容が、ダラダラと仕事をしているせいで終わらない。」
となった場合に、残業として認められるのは難しいです。
そもそも、通常業務の量が多い所属だと、こなせないことに関して「個人の処理能力が不足しているのではないか」という評価になるリスクがあります。
時間外勤務の多さは、人事評価の評価項目において、良い影響を及ぼさない可能性があります。
サービス残業問題は無くせないのか?
個人的な意見にはなってしまいますが、そう簡単には無くならないでしょう。
各自治体含め、何もせずにいるわけではありません。
・資源の有効活用
・定時退勤日の設定
・雑務の軽減
・手続き簡略化
など、色々な施策で職員の超過勤務時間の短縮を図っています。

それでも現代の情報量の多さ、変化の速さに精一杯対応していこうとすると、なかなか上手くいかないんですよね・・
一方で、予算要求は前年度比に対し、同程度もしくは数%削減を上限として計上するのが基本です。
つまり、努力して縮減を図っても、それ以上に業務が増えていくので残業時間は変わらない。
しかし、人件費は予算編成時の要求で、原則増やす事はできない。
このため、サービス残業をせざるを得ない状況が生まれ続けるということです。
公務員のサービス残業の改善には長い時間がかかりそう

最近、民間企業では働き方改革が進み、ホワイトな職場が増えてきました。
サービス残業は「悪」であるとして、排除しようという動きが進んでいます。
しかし、公務員の職場で、サービス残業をなくすことは、まだまだ時間が掛かる問題です。
なぜなら、サービス残業の根底にある問題を解決する必要があり、公務員の業務の在り方や人件費の制約が大きな課題となるでしょう。
多忙な部署では、定時を大幅に過ぎても仕事が終わらないことが多く、超過勤務が常態化しています。

それでも、全ての残業代を請求するのは現実的に難しい。と感じている職員が多いのではないでしょうか。
私は100時間以上の残業をしても、実際に請求したのはそのうちの10時間だけでしたが、これは私だけでなく、同様の経験をしている職員はたくさんいます。
また、現時点でたとえ「サービス残業は違法」として声を上げても、多くの部署で常態化しており、周囲からの賛同を得にくいでしょう。
むしろ、職場の秩序を乱す存在として扱われ、上層部からの評価に悪影響を及ぼすこともあるかも知れません。
公務員組織というのは、そのような表面では見えない課題が結構あります。
このようにサービス残業を無くすには、個々の職員の声だけではなく、国も含めた組織全体での改善が必要です。
しかし、これは時間のかかる取り組みであり、すぐに解決できる問題ではありません。
「サービス残業をさせられている」ということだけにフォーカスして、ネガティブになるのではなく、自身の業務を少しでも効率化させ、退勤を早めるチャレンジをする
このようなワークライフバランスを考えていく方が良いでしょう。
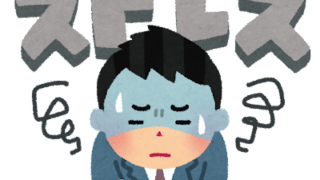
残業代は気にしなくても資産は増やせます

たくさん働いても、残業代は請求できずに対価が得られないジレンマが公務員にはあります。
時給換算してしまったり、どうしてもネガティブな気持ちが生まれてしまいがち。
そこで、視点を変えた資産形成にシフトチェンジすることをオススメします。
なぜなら、公務員の大きな強みは、安定した雇用と定期昇給による「守りの強さ」にあります。
そのため、現状の給料から支出を最適化して堅実にお金を残す。
そして、余剰分から運用に回してお金を増やしていく。
これが、最も効率的で簡単な資産形成の方法です。
さらに、金銭的な不満も解消され、残業代というチマチマした金額にストレスを抱えることなく日々働いていくこともできます。
実際、私も一定金額の資産に到達することで、残業代は気にならなくなりました。

お金に固執することがなくなって解放された感がありましたね
たとえば
・保険や定期料金(固定費)の見直し
・住宅ローンの借り換え
・日々のコンビニ買いや外食の最適化
など、支出を抑えつつ賢くお金を「守る」方法は数多くあります。
ただし、その判断には専門的な知識が必要不可欠です。

より最適な選択のためには「知識」と「情報」が欠かせません
【本当は教えたくない】中立系のFP無料相談
「支出を最適化しようにも、そんな知識を学ぶ時間はない・・」
「とにかく手早く最適解を教えてほしい」
少しでもそう思ったあなたにおすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(FP)との無料相談。
特に、特定の金融機関に偏らない「マネプロ」のFP無料相談がオススメ。
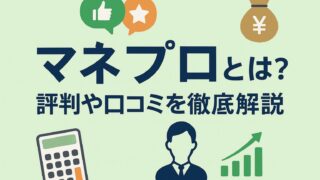
中立的な立場のFPが、保険・投資・税金・家計見直しなどあらゆるお金の悩みに一気通貫で対応。

ゼロ円で、公務員として堅実に生きるあなたに最適なアドバイスをしてくれます。正直ヤバイです。
無理な押し売りも当然ありませんし、対面+オンラインでどこでも対応可能。
収入を「増やす」より、まず今あるお金を「守る」力を高める。
守ったお金を攻めに使って増やしていく。
これが、公務員としての賢いお金の増やし方(資産形成)の第一歩です。
まずは、90%以上のサラリーマンが知らないお金の秘密をプロから聞いてみてください。
公務員のサービス残業(サビ残)問題は根深い【まとめ】
公務員のサービス残業について解説してきました、まとめると以下の通りです。
公務員のサービス残業の現状
公務員の中にはサービス残業が存在しないと考える人もいるが、実際には多くの公務員が適切な残業代を受け取れていない。
特に忙しい部署では、自主的なサービス残業が発生しやすい。
多忙な部署の超過勤務の実態
特に福祉、財務、医療、警察などの現場では、超過勤務が常態化している。
時間外の労働が月100時間を超えることも珍しくなく、精神的な負担が大きく、長期療養休暇に入る職員もいる。
(例)
休日出勤:業務量が多すぎて通常の勤務時間では終わらない
緊急対応:予定外の対応が頻繁に発生し、結果的に残業が増える
精神的負担:常に忙しい職場環境が疲労やストレスを引き起こしやすい
公務員と労働基準法の関係
公務員は一般の労働者と異なり、労働基準法が適用されない部分がある。
ただし、代わりに国家公務員法や地方公務員法によって、労働時間や休暇に関する規定が設けられている。
残業時間の上限
原則、月45時間、年360時間と定められているが、忙しい部署では月100時間未満、年720時間まで延長できる場合もある。
残業代と残業時間上限は別問題
残業時間の上限は設けられているが、ひとりひとりが上限分までの予算枠は無い。
結果請求できる残業代には限度があり、以降はサービス残業となる。
サービス残業は無くならないのか?
各省庁や自治体でも勤務時間の縮減に尽力しているが、現代の情報量の多さに加え、予算の問題が解消できなければ無くならない。
サービス残業告発のリスク
サービス残業を告発する方法として、人事院や人事委員会に相談する手段があるが、リスクも伴う。
(例)
上層部から注目を浴び、悪目立ちの可能性
職場の人間関係が悪化する可能性
体験談:サービス残業が当たり前だった
過去に毎月100時間以上の残業をしていたが、請求したのはそのうちの10時間分だけだった。
予算制限が厳しいうえ、正直に残業時間を報告すると、余計な報告業務が増えることを避けたため。
サービス残業改善への課題
民間企業では働き方改革が進み、ホワイトな職場が増えているが、公務員の職場ではサービス残業をなくすには時間がかかる。
サービス残業の根本原因は、業務の在り方や人件費の制約にあり、組織全体での改善が必要である。
変化には時間が必要
定時を超える業務が常態化しており、全ての残業代を請求するのは難しい。
声を上げても周囲の賛同を得にくく、職場の秩序を乱す存在として評価が下がる可能性がある。
公務員の残業代はあくまで、予算あってのものです。
とはいえ、安定は捨てがたいが割に合わないと感じる方もいるのではないでしょうか。

残業代をいちいち気にするのもストレスですね
そこで、お金に囚われない働き方へとシフトチェンジすることをオススメします。
具体的には支出の最適化と資産運用の合わせ技。
もし、あなたの根底に
・収入を増やして家計の足しにしたい
・新しい物品の購入費用に充てたい
・少しでも損をしたくない
という、お金への思いがあるなら、まず支出の最適化に目を向ける方が圧倒的に楽です。
なぜなら、収入を増やすことと支出を減らすことは同じだからです。

実際、公務員にとって1万円増やすよりも1万円支出を減らす方が現実的です。
そのための第一歩は、効率的な家計管理についてお金の専門家からアドバイスを得ること。
→あなたの支出が何万円減らせるか分かる「マネプロ」の無料相談
逆に、このアクションを起こせないと、今後も立場をおびやかすリスクを負ってしまったり、思わぬ損失を招く可能性も。
「公務員でもお金を増やしたい」と思う方は、支出を減らすことも、セットで意識してみてください。