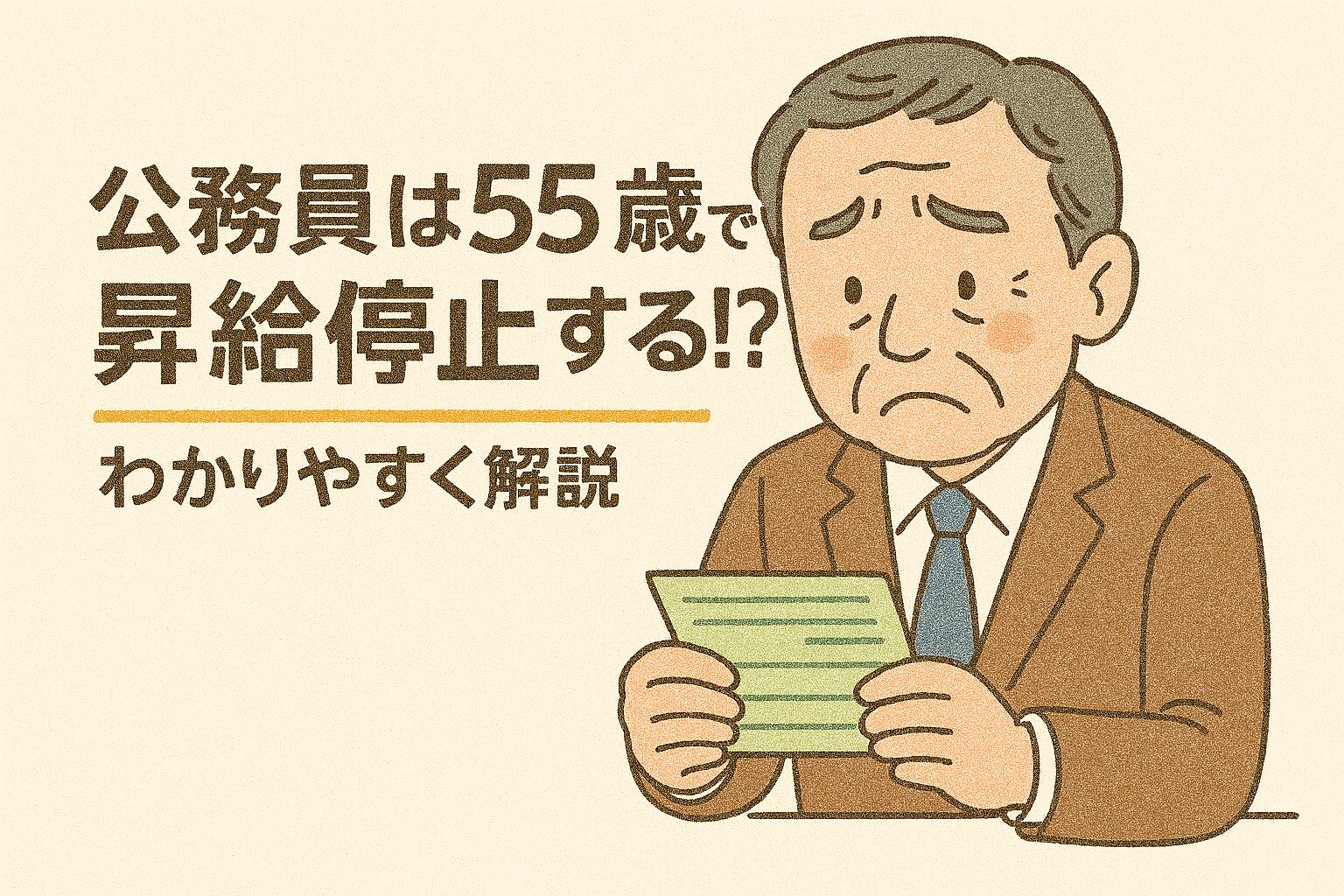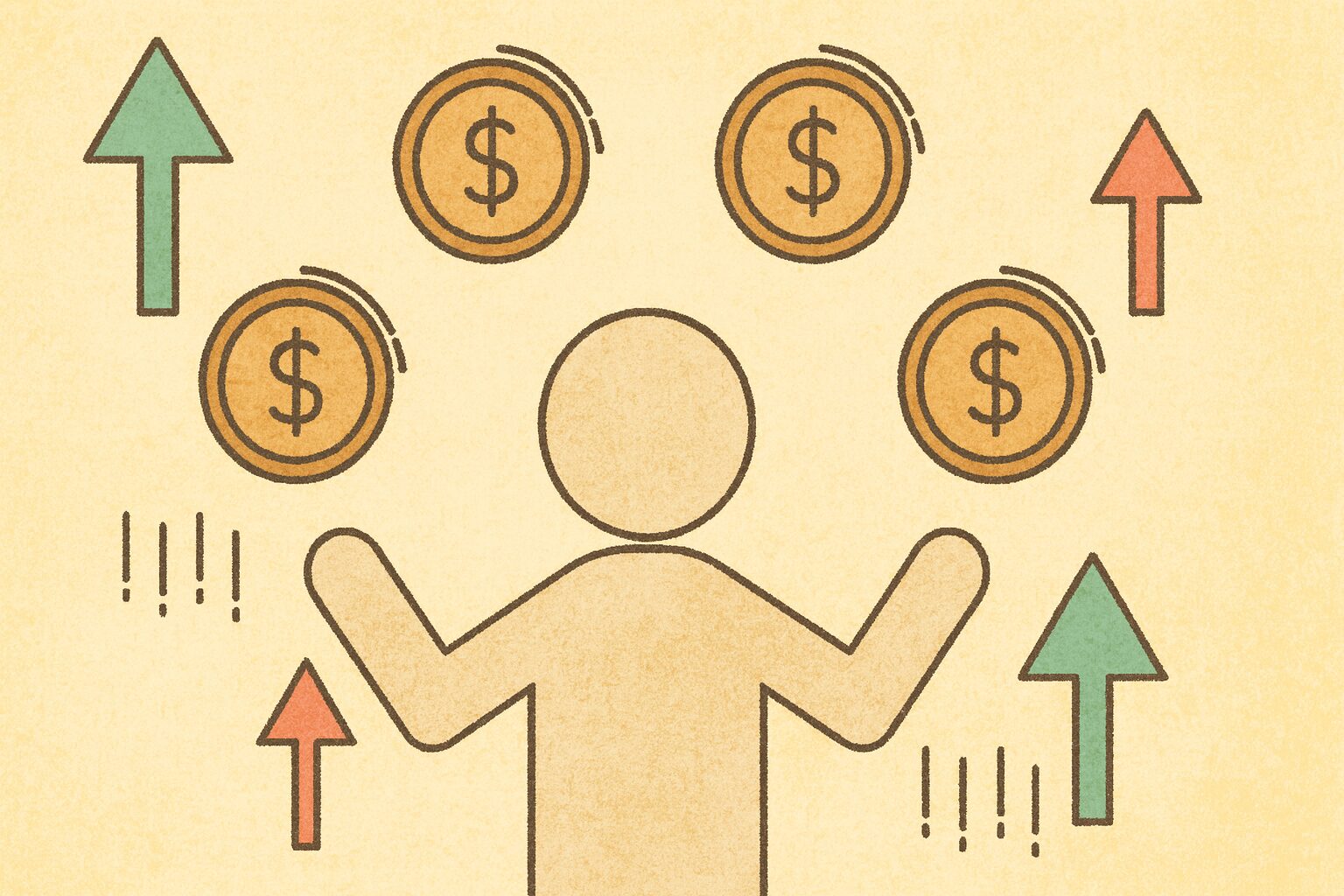公務員のボーナスがおかしいと言われる件について【元公務員が解説】

「公務員のボーナスって多い?少ない?」
「公務員がボーナスを増やす方法はある?」
など、公務員のボーナスについて色々と気になっていませんか?
民間企業は業績で金額が上下するから分かりやすいですが、公務員って利益を追求していないのに、どうやって決めてるの?ってハナシですよね。

ひとりひとり差が付いたりするものでしょうか・・
この疑問について解説していきます。
結論としては、公務員のボーナスは民間企業の平均に沿って、支給率が決められています。
なぜなら、人事院という機関が民間企業の動向を調査・検討をして、政府に勧告するためです

つまり、全くおかしなことはなく、妥当な金額が支給されているということです。
公務員のボーナス事情について具体的に解説していきます。
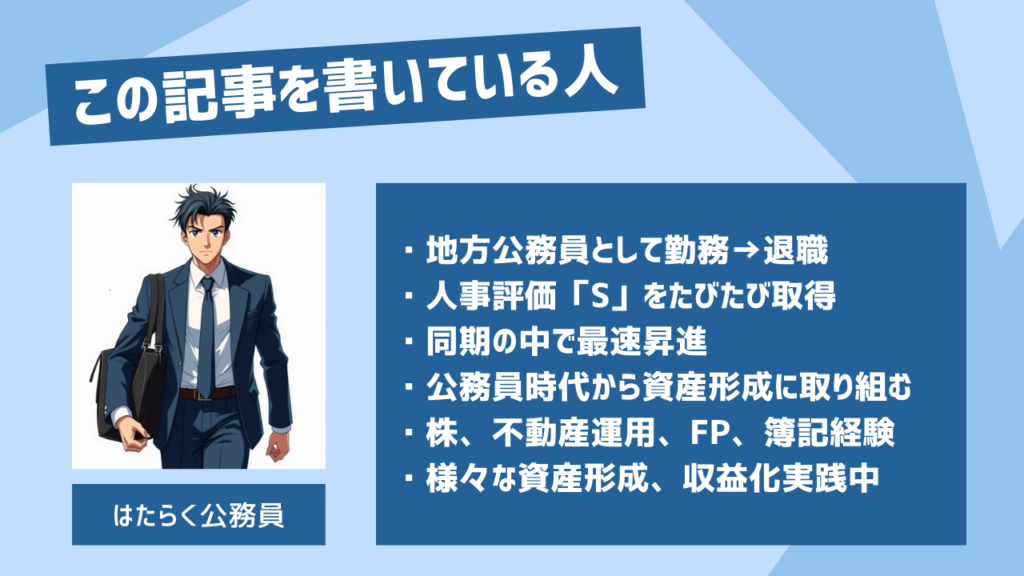
→”ひよっこ”からボーナスUP&最速昇進できたノウハウはコチラ
厳密には公務員にボーナスというものはありません。
世間一般でいうボーナスに代わり、公務員に支給されているのは「期末・勤勉手当」です。
手当の仕組みを理解して、着実に資産を積み立てていきましょう。
公務員のボーナスはなぜおかしいと言われる?

公務員のボーナスが民間企業と比較して適切かどうかについては、様々な意見があります。
その中でも、おかしいと言われる要因は2つ。
1.民間企業からすると、ノルマや業績が公務員にはないのに貰いすぎ。
2.公務員からすると、ボーナスの金額が評価に比例していない。
こんな意見が多くみられます。
この点について具体的に解説していきます。
公務員のボーナスは支給割合が多くみえる?
民間企業の視点で考えてみると、公務員のボーナスが多いか少ないかは、人それぞれの勤め先、価値観や働き方によって異なります。
なぜなら、公務員のボーナスは、民間企業の平均値を基準として調整されているからです。
これは、毎月の給料も同じです。


人事院という機関が、中小企業の動向を調査して公務員の適性な給与について政府に勧告し、改定しています
多く支給されている企業も、そうでない企業もひっくるめて平均が導き出されます。
つまり、世間一般的に見て公務員のボーナスがケタ外れな金額になることはありません。
また、公務員のボーナスは
「月給×支給割合」です。
ボーナスの算定基礎となる公務員の月給は
・役職
・職務内容
・経験年数
などに応じて決定されますが、特に若年層公務員の給与水準は、一般的に民間企業よりもやや低めに設定されています。
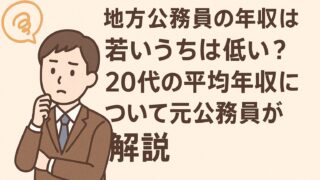
たとえば
・民間企業勤務Aさん:月給25万円。ボーナスは月給の1.5ケ月分を年2回支給
250,000円×1.5×2=750,000円(ボーナス)
250,000円×12=3,000,000円(給料)
→3,750,000円(年収)
・市役所職員Bさん:月給23万円、ボーナスは月給の2ケ月分を年2回支給
→230,000円×2×2=920,000円(ボーナス)
230,000円×12=2,760,000円(給料)
→3,680,000円(年収)
このように、支給率が多少多めに設定されていても、実際は年収で見るとそこまで伸びません。
現役公務員はもっとボーナスをもらいたい?
一方で、公務員側に立ってみると、「もっとボーナスを支給してほしい」という声もあります。
なぜなら、基本給が高い民間企業の方が、ボーナスが高額であると感じられるためです。

確かに、同年代で公務員と同じような入社難度の企業だと、企業の方が多く貰っていましたね
また、日頃の業務の多さも「割に合わない」と感じさせる要素があります。
実際に、近年の傾向を見ると、公務員離れが進んでいるというニュースも見られます。
人手不足や少子化の影響で、大学生の就職活動は売り手市場が続いています。
地方公務員の受験者数は10年間で3分の2まで落ち込んでいて、採用時期の拡大や試験制度を見直す自治体もあります。
(引用:yahooニュースより)
これは、シンプルに
「給与や仕事の内容が魅力的でないから人気が無い」
ということを示す結果です。

いずれにしても、主観・客観で感じ方は違いますし、判断が難しいところ。
ですが、公務員のボーナスは民間企業に沿って適正に設定されているため、少なすぎる金額ではないとも言えます。
民間企業と公務員との具体的な比較
民間企業と公務員の給与較差を表す計算は複雑です。
そこで、少し古いですが2023年の人事院勧告からざっくり抜粋した結果を示していきます。
【公務員と民間企業の月額給料の比較】
・調査対象の全民間企業社員平均・・407,884円
(従業員50人以上の規模の企業における部長・課長・課長代理~・・係員まで)
・国家・地方全公務員平均・・404,015円
(行政組織の部長・課長・課長補佐・係長・主任・係員まで)
官民較差・・▲3869円(この分民間企業の方が多くもらっている)

いやいやこんなに貰ってないよ!と思う方もいると思いますが、あくまで全年代&広い役職での総支給額の比較です。
保険料等が控除された後の手取り額ではないことに注意。
以上の結果から、2023年は民間企業との格差分を埋めるため、公務員の給与とボーナスの支給月数を引き上げました。
そして現在、物価高騰から民間給与が上がっており、公務員も準じて上がっています。
この給与調査結果からも、民間企業と公務員間の乖離はそこまで大きくなく、公平性が保たれていることが分かります。
【ホントにおかしい?】公務員のボーナスを具体的に解説

公務員にはボーナス(賞与)という概念はありません。
なぜなら「期末勤勉手当」という手当が、民間企業と同時期に支給されているからです。
その為、民間企業のボーナス(賞与)とは少し意図が異なります。

ここでは分かりやすくボーナスと表現しますが、これは世間的に分かりやすく浸透しているからです。
マスコミやニュースでも同じ意図で使われています
実際に公務員のボーナスがおかしいのかどうか、実態を解説していきます。
公務員に支給されるボーナスの現状【平均支給額とその内訳】
年間の期末勤勉手当(ボーナス)支給月数について、以下の図をご覧ください。
【公務員の期末勤勉手当年間支給実績】
| 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | |
| 令和3年度 | 2.4月 | 1.9月 | 4.3月 |
| 令和4年度 | 2.4月 | 2.0月 | 4.4月 |
| 令和5年度 | 2.4月 | 2.1月 | 4.5月 |
これを踏まえた、2023年一般職国家公務員の年間平均ボーナス支給額は、おおよそ135万円。
この金額は、地方公務員も同様で月額給与の約4.4倍に相当します。

1年間での勤務期間が短ければ、ここから支給割合も減少します

令和3~5年度までは順調に増えていますが、令和2年度は経済不況に伴い引き下げられていますね・・
なお、期末手当は、一定期間における在職期間などから算出されて支給されるもの。
勤勉手当は在職期間に加えて、勤務成績や人事評価による職務遂行能力などに応じて支給されます。

国家公務員・地方公務員・教員ではそれぞれ額が違う?
公務員といっても、さまざまな職種があります。
しかし、結論として国家公務員、地方公務員、教員のボーナス支給率は基本的には同じです。
なぜなら、国家公務員のボーナス支給率が基準となり、地方公務員や教員のボーナス支給率は、それに合わせる形で支給されているからです。

というより教員は地方公務員なんです・・
ただし、支給率は一定の基準に基づいて決定されているものの、手当の加算による支給額の変動があります。
具体的には、国家公務員や地方公務員の役職・職務内容に応じて各種手当が支給されます。
この中に、管理職手当や特別職手当なども含まれていて、教員であれば教員特別手当といったような加算が付きます。
このように、公務員のボーナスは職種や役職に応じた手当によって、異なるように見えますが、ベースは同じになっています。
公務員のボーナスがおかしいかどうか忖度ナシで判断すると・・?

ここでは、元公務員である私の体験に基づく個人的な考えを述べていこうと思います。
忖度はしませんが、あくまでひとつの考え方として参考にしてもらえれば幸いです。
組織内でもボーナスへの捉え方が異なる
公務員業界でも
「わぁ、こんなにもらえて嬉しいな」
という人もいれば
「こんなに働いてこの額か・・・」
という2つの捉え方が存在します。
なぜなら、公務員業界でも、能力や仕事への取り組み方には大きな差があるからです。
そのため、給与に関する不満や葛藤がココで生まれてしまいがちです。

要は仕事がデキる人とイマイチな人がいるということです・・
実際に私自身、長年公務員として働いてきて
・仕事を全力でこなしている人
・お世辞にも全力で仕事しているとは言えない人
この2人に対して同額のボーナスが支給されていました。
つまりまとめると
・誠実に一生懸命仕事をこなす公務員
→ボーナスは少ないと感じる
・ほどほどに仕事をこなす公務員
→そこそこボーナスを貰えると感じる
というように分かれているということ。
外でも内でも、考えがバラバラなのでおそらくこの答えはずっと出ないと思います。
無能なベテラン勢は批判の的になりやすい
外部から公務員のボーナスがおかしいと言われてしまう要因のひとつに、ベテラン職員の給与の高さが挙げられます。
なぜなら、仕事にあまり前向きでなくとも、年齢にともない確実に昇給していくからです。
実際に、50歳を超えるベテランは、中小企業の年収を上回る傾向にあります。
その結果、市民のニーズを満たせない微妙なベテランでも給料は高い。
これが、公務員批判にもつながっています。

・仕事が遅い
・接遇ができてない
・不祥事ばっかり
などのクレームはしょっちゅうもらいます。

感謝の言葉をもらえる一方で、失望の声も届く・・・
これは、その時対応した職員の能力によって、変わってしまうのが実情。
そのため、文句を言わせないほどの行政サービスを提供し、高い満足度を維持する。
職員ひとりひとりの意識とスキルアップが大事です。
業績評価でボーナスを分けるのが難しい
公務員という職業は数値目標で判断するのが難しい職業です。
なぜなら企業とは異なり、社会的な使命や公共の利益を追求することが主な使命で、数字だけで決められる世界ではないからです。
実際に、管理職と勤務評価についての話になった時
「あからさまでない限り、評価を分けるの無理だよね」
とキッパリ言っていました。
そのため、ボーナスの支給においても、業績や成果で細かく支給額を分けることが難しいのが実情です。

公務員のボーナスの支給方法が適切かどうかは、多くの議論の余地があると思います。
公務員のボーナスは適正なので下げる発想はやめたほうがいい
景気が悪くなってくると時折聞かれるのが
「公務員の給料やボーナスは税金なんだから下げるべき」
という意見です。
確かに、日本全体で皆が厳しい状況である中、公務員だけ安定しているのは不満を感じやすいです。
しかし、公務員のボーナス等カットについては、最終手段にするべきです。
なぜなら、景気の低迷と公務員の待遇は別問題として、切り離した方が良いからです。
例えば、民間企業であれば人件費削減のメリットは
・設備投資
・株価上昇
・決算改善による融資拡大
などが期待できますが、公務員はこの通りではありません。
一方で、以下のようにデメリットはもりだくさんです。
・支出が絞られ経済に悪循環(物を買わない)
・職員のモチベーションの低下(サービス低下)
・人材不足の加速(行政運営危機)

むしろ一般市民に跳ね返ってしまいそう・・
また、景気が低迷する原因は、非常に複雑です。
そのため、公務員の人件費削減というスポット的な対処では、どうにかなるものではない。
というのが個人的見解です。

景気改善のカギは国外も含めて「循環させること」です
このように、官民待遇の比較と不満で報酬カットを望むのは大局的な視点とは言えません。
公務員の仕事の特性や社会的な役割を考慮すると、ボーナスを安易に引き下げるような意見は、決して簡単に受け入れて良い問題ではないと感じます。
直近ではコロナウイルス感染症による経済不安もありましたが、そのような場面で地域や市民を支えていたのは行政の職員でもあります。

ましてや近年では物価の上昇が進み、賃金もあわせて上昇していかなければ景気は冷え込む一方です。物価と賃金は連動していかなければいけません
いかに減らすかではなく、いかに増やすかに注目してほしいところです。
・公務員がボーナスを支給されることに疑問を感じられてしまう背景には、人材のバラつきや年功序列の組織体系が原因。
・業績評価もしにくいため支給額で差が付かない
・安易なボーナス等の引き下げについては慎重に検討するべき
ボーナスがおかしいと感じる公務員の解決策
ここまでで、現役公務員として
「働きに対してボーナスの額が見合ってない!」
「もっと報酬を上げてほしい!」
と思ったらやることは1つ。
人事評価で上位を目指してください。
理由はシンプルに3点です。
1.昇給幅が増える
2.ボーナスが加算される
3.昇進が早まって生涯年収が増える
そのため、戦略的な働き方で高い人事評価を得る必要があります。
また、誤解を恐れず言いますと、高評価によって築かれた信頼はそう揺らぐことはありません。
一度”シゴデキ認定”されると、その後昇進を含めた良い流れに入っていくことができます。
具体的には
「この人はデキるから、言っていることも間違いないだろう」
「彼の評価は良いと聞いている」
といったプラス効果が生まれ続けるということ。
まとめると、人事評価で最大評価を戦略的に狙って、圧倒的信頼感を構築してしまいましょう。
これで、評価と報酬の両方が付いてきます。

できる限り「A」や「S」を叩き出します
とはいっても、何も考えず働いていても、あなたの評価は一向にあがりません。
そこで、noteで評価を最大限上げていくためのノウハウをまとめました。
・24000字を超える大ボリューム
・購入者特典つき
・限定価格(今後値上げ)
・note規定に基づく返金申請アリ

おそらくここまで意識して日々働いている人は少ないかと
いずれにしても、今がコスパ◎の絶好機です。
ボーナスをもっと上げたいと思っているのであれば一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
公務員のボーナスがおかしいのは表現の問題【まとめ】

この記事では公務員のボーナスがおかしいと言われる問題について解説してきました。
ポイントをまとめると以下の通りです
・公務員のボーナスは正確には期末・勤勉手当。業績に応じた賞与ではない。
・2023年の一般職国家公務員の平均ボーナス支給額は約135万円。地方公務員も同様で、月給の約4.4倍に相当。
・ボーナスの内訳は期末手当と勤勉手当に分かれ、期末手当が大きな割合を占める
・国家公務員、地方公務員、教員のボーナス支給率はそれぞれの職種や役職に応じた手当の加算があるものの、基本的には同じで国家公務員の支給率が基準。
・公務員のボーナスが高額に感じられることがあるが、公務員の給与は民間企業の平均値を基準に調整されている。
・2023年の人事院給与調査では、民間企業と公務員の平均月給には約3,869円の差があり、その差を埋める措置がされたように、公平性が保たれている。
公務員のボーナスは民間企業の平均値をとった支給額ですが、若年層で同年代の民間企業と比較するとやや物足りなさを感じる場合もあります。
そのため、もし今あなたがボーナスが少ないと感じているのであれば、資産形成を早い段階で始めて給与に依存されない環境を自分でつくることをオススメします。

とはいっても、はじめは何をどうしたら良いか全くわからないと思います。
そこで、ゼロからでも手間なくできる資産形成法を経験に基づいて配信しています、
気になる方はチェックしてみてくださいね。
公務員向け資産形成講座はこちらから
今メルマガ登録すると
「元公務員が解説する公務員特化型の蓄財法」
を期間限定プレゼント!
(下記よりメールアドレス登録のみ!10秒で完了します)
※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。
※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。
※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。
※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。